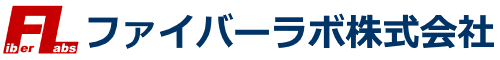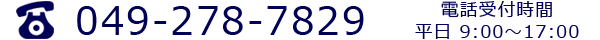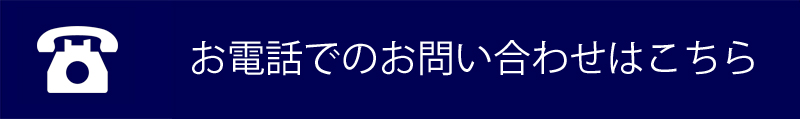用語説明(仕様に使われている用語の説明です。仕様をご覧になるとき参考にしてください。)
投稿日 : 2016年9月1日
最終更新日時 : 2016年9月14日
投稿者 : fiberlabs
| 光学系 |
有限遠補正 |
対物レンズだけで中間像(接眼レンズでみるための像)を作る光学系です。対物レンズもと接眼レンズの距離が決まっています。 |
| 無限遠補正 |
対物レンズに入った光を平行光にして結像レンズに入れ中間増像を結像します。対物レンズと結像レンズ間は平行光で距離が自由なのでビームスプリッタやフィルタなどの光学系を挿入し易くなります。現在、主流の光学系です。 |
| 単眼鏡筒 |
1コの接眼レンズで片眼で観察します。 |
| 双眼鏡筒 |
2コの接眼レンズで両目でみます。見る人に合わせて眼幅調整と視度調整ができます。 |
| 3眼鏡筒 |
2眼鏡筒に撮影用の鏡筒が加わり3眼になっています。カメラを装着できます。 |
| 接眼レンズ |
対物レンズや結像レンズが結んだ中間像を拡大して観察するレンズです。WHと書かれた広い視野の10Xレンズが一般的です。 |
| ハイアイポイント接眼レンズ |
離れた位置から観察できる接眼レンズ。メガネをかけたままの観察に便利です。 |
| レチクル接眼レンズ |
照準のための十字やマイクロスケールの入った接眼レンズ。 |
| 視度調整 |
接眼レンズを観察者の視力に合わせるための調整です。視度調整により眼の疲労が少なくなり、対物レンズの倍率を変えても焦点がずれなくなります。 |
| 対物レンズ |
観察物の像を最初に作るレンズです。顕微鏡性能を決める最も大切な部品です。 |
| 収差補正対物レンズ |
アクロマート |
赤と青2色の色収差を補正したレンズ。視野中心にピントを合わせると端がぼける。 |
| プランアクロマート |
赤と青2色の色収差と像面湾曲収差を補正したレンズ。視野中心にピントを合わせても端がぼけない。 |
| プランアポクロマート |
赤と青と緑3色の色収差と像面湾曲収差を補正したレンズ。視野中心にピントを合わせても端がぼけない。NA(開口数)が大きく分解能がよい最高級レンズ。 |
| 作動距離 |
ピントがあったときの対物レンズ先端からサンプル面までの距離です。 |
| (WD : Working distance) |
倍率の大きいレンズほどWDは短くなります。 |
| 長作動距離対物レンズ(LWD :Long working distance) |
作動距離が長くなるように作られたレンズです。倒立顕微鏡のように観察対象物とレンズの間にスライドガラスやシャーレの底のような厚みのあるものが介在するとき必要になります。 |
| 開口数(NA : Numerical aperture) |
対物レンズに入る光の範囲をあらわします。NAが大きいほど広い範囲の光が入るので分解能が高く、像が明るくなります。 |
| レボルバ(ノーズピース) |
対物レンズを装着して回転させる円板。4穴はレンズ4コ、5穴は5コ装着できます。 |
| ステージ |
観察対象物を載せる台です。ダイヤルでX-Yに移動させます。 |
| コンデンサ |
照明光を集めるレンズ装置です。開口絞りで光量調節します。 |
| アッベコンデンサ |
凸レンズ2枚で構成される最も一般的なコンデンサ |
| 開口絞り |
コンデンサの中にある絞りで、標本を照明する光の開口数を調節します。開口数を絞るとコントラストがよくなりますが、明るさが低下し分解能が悪くなります。絞りを広げると明るくなり、分解能がよくなりますが、コントラストが低下します。 |
| 視野絞り |
観察している範囲だけが照明されるようにする絞りです。観察範囲より僅かに広い |
| 照明で観察します。 |
| 明視野観察 |
対象物を均一な光で照らし色や明るさを観察する最も一般的な観察法です。照明により視野全体が明るく見えます。 |
| 暗視野観察 |
対象物に側面から光をあて対象物からの散乱光や回折光を観察します。照明光が対物レンズに直接入らないので視野が暗く像が明るく見えます。無染色で観察できます。 |
| 位相差観察 |
無色透明であっても屈折率が異なると位相がずれます。位相のずれた回折光を干渉させて明暗のコントラストに変換し観察します。 |
| 蛍光観察 |
紫外や可視の励起光をサンプルに照射し、発生する蛍光を画像として観察します。試料を蛍光色素で染色するのが一般的です。 |
| 偏光観察 |
試料に偏光を照射し、試料による偏光面の回転を明暗や色の変化として観察します。 鉱物、結晶、高分子などの観察に用いられます。 |
| 視野数(FN : Field number) |
接眼レンズで観る中間像の直径(mm)をいいます。視野数が大きいほど標本の広い範囲を観察できます。 |
| 実視野(FOV : Field of view) |
接眼レンズで観察している部分が標本のどの範囲かを示したもので次式の関係があります。 FOV=FN(視野数)/M(対物レンズの倍率) |
| 同焦点距離(PFD : Parfocalizing distanceof the objective) |
対物レンズの長さ(ネジ部を覗く)と作動距離を足した距離です。この距離が45mmと一定にしてあるので倍率の違うレンズをレボルバで切替えてもピントが合っています。 |
| 焦点深度(DOF : Depth of field) |
1点にピントを合わせたときに同時にピントが合って見える範囲です。焦点深度が深い(長い)ほど厚みのある試料でも全体をはっきりみることができます。深い(長い)ほど厚みのある試料でも全体をはっきりみることができます。 |
| 分解能 (Resolving power) |
微小な2点を見分けることができる最小距離です。この距離が小さいほど高分解能です。 |